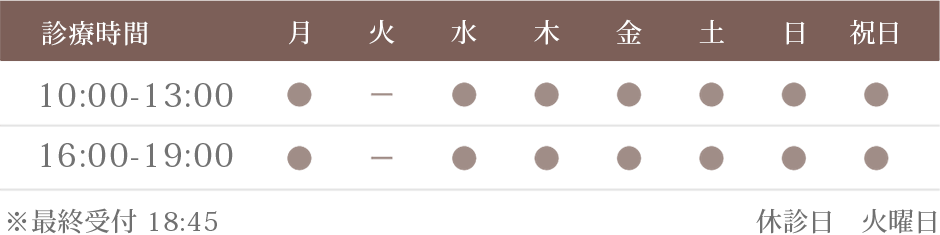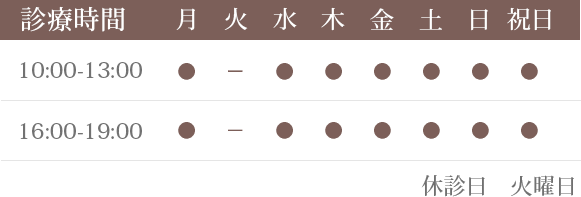BLOG
愛犬のうんちがゼリー状に?粘膜便の原因と対処法|高齢犬でも安心の短時間治療

広尾・恵比寿・西麻布・南麻布を中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」です。
愛犬の便は毎日見るものですが、いつも健康的な良い便である訳ではありません。時には便がゆるくなってしまい、その便にゼリー状のものが付着することがあります。そのような便がなかなか治らないと「犬 うんち ゼリー」というキーワードで検索される飼い主様も多いのではないでしょうか。
今回は粘液便について、原因や治療方法、予防法などをご紹介します。
■目次
1.粘液便とは?
2.粘膜便の主な原因
3.粘液便の危険性
4.自宅でできる応急処置
5.動物病院での治療方法
6.粘膜便の予防法
7.まとめ
粘液便とは?
粘液便とは、犬の便に透明または半透明のゼリー状の物質が付着している状態を指します。これは腸から分泌される粘液が過剰に出ている状態で、軽度の場合は一時的なものかもしれませんが、重度の場合は何らかの健康問題のサインかもしれません。
粘液便を見つけたときは心配になるかもしれませんが、落ち着いて対応することが大切です。早期発見・早期治療が何より重要であるため、症状が続く場合は迷わず獣医師に相談しましょう。
粘膜便の主な原因
粘液便の主な原因には、以下が挙げられます。
<消化器系の炎症>
大腸炎や腸炎などの炎症性疾患は、犬の腸内で過剰な粘液分泌を引き起こす主な原因の一つです。炎症があると、腸の内壁が刺激され、通常よりも多くの粘液が分泌されます。この粘液は腸内の保護機能を果たしますが、炎症があるとその量が増え、粘液便として排出されることがあります。
<ストレス>
新しい家族が増える、旅行や引っ越しなどによる環境の変化がストレスの原因となり、腸の働きに影響を与えることがあります。そのため、腸の動きが乱れることにより、粘液便が発生することがあります。
<食事の変化>
急激な食事の変更や、消化に悪い食べ物を与えることも粘液便の原因となります。犬の消化器系は、突然の食事の変化に対応するのが難しいこともあり、これが腸を刺激して粘液便を引き起こすことがあります。そのため、特に新しいフードやおやつを与える際には注意が必要です。
<寄生虫感染>
ジアルジアなどの寄生虫が腸に寄生すると、腸管が炎症を起こし、粘液便や血便が見られることがあります。寄生虫感染は糞便検査で確認でき、適切な駆虫薬による治療が必要です。
粘液便の危険性
粘液便を放置すると、症状が悪化したり、脱水のリスクが高まったりする可能性があります。特に子犬や高齢犬、持病のある犬では注意が必要です。
自宅でできる応急処置
自宅でできる応急処置としては、まず十分な水分補給が重要です。また、消化の良い食事(茹でた鶏肉と白米など)を少量ずつ与えることで、腸を休ませることができます。ただし、これらは一時的な対処法に過ぎません。症状が24時間以上続く場合や、以下の症状が見られる場合は、すぐに獣医師の診察を受けてください。
・食欲不振
・血便
・嘔吐
・元気消失 など
動物病院での治療方法
動物病院では、症状や原因に応じて適切な治療が行われます。一般的には、点滴による水分や電解質の補給、整腸剤や抗生物質などの投薬、場合によっては寄生虫駆除薬の投与などが行われます。
また、免疫疾患や腫瘍などが原因となっていることもあるため、さらにレントゲン検査や超音波検査、CT検査を行うことがあります。
粘膜便の予防法
粘液便の予防には、以下のような方法があります。
<定期的な健康診断>
年に1〜2回の健康診断で、潜在的な問題を早期に発見できます。
<適切な食事管理>
質の良いドッグフードを適量与え、急激な食事の変更を避けましょう。
<ストレス軽減>
規則正しい生活リズムを保ち、十分な運動と休息を与えましょう。
<寄生虫予防>
定期的な駆虫を行い、寄生虫感染を予防しましょう。
<衛生管理>
食器や水飲み容器などを清潔に保ち、定期的に洗浄しましょう。
まとめ
最後に、愛犬の健康を守るのは飼い主様の役目です。
日頃から愛犬の便の状態をよく観察し、変化があればすぐに気づけるようにしましょう。粘液便が見られた場合は、慌てずに適切な対応を心がけることが大切です。そして、心配な症状が続く場合は、迷わず獣医師に相談することをお勧めします。
当院では大切な家族の一員である愛犬の健康を守るため、経験豊富な獣医師が心を込めて診察します。安心と信頼のケアを提供する当院へぜひお越しください。
広尾・恵比寿・西麻布・南麻布中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」では定期健診に力を入れており、病気の予防と長期健康維持のお手伝いをしております。