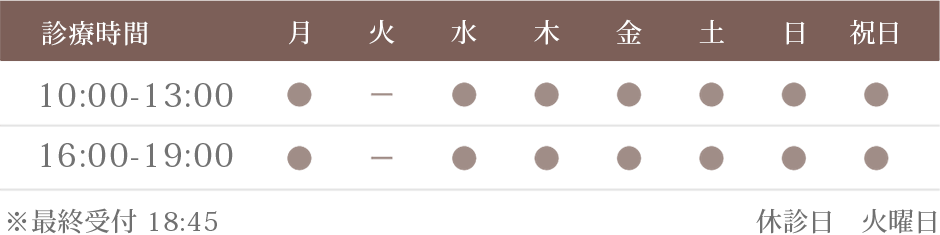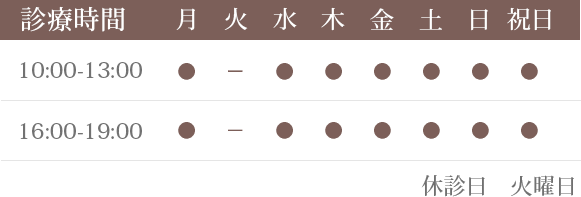BLOG
愛犬や愛猫が突然ガクガク! |てんかん発作かも?知っておきたい症状と対処法

広尾・恵比寿・西麻布・南麻布を中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」です。
愛犬や愛猫が突然ガクガクとけいれんを起こす場面に直面したことはありませんか?そんなとき、考えられる病気のひとつに「てんかん発作」があります。初めて愛犬や愛猫の発作を目にしたときは驚き、どう対処すればよいか戸惑うことが多いでしょう。しかし、飼い主様が冷静に対応することが、愛犬や愛猫の安全を守るために非常に重要です。
今回は犬や猫のてんかん発作について、症状や対処法などを解説します。
■目次
1.犬や猫のてんかん発作について
2.てんかん発作の定義と一般的な症状
3.犬と猫での発症頻度や年齢層の違い
4.てんかんと他の発作性疾患との違い
5.てんかん発作時の対処法と応急処置
6.診断方法
7.治療方法
8.まとめ
犬や猫のてんかん発作について
犬や猫のてんかんは、主に以下の「症候性てんかん」と「特発性てんかん」の2種類に分けられます。
・症候性てんかん:脳腫瘍や脳炎、頭部外傷によって発作が引き起こされます。
・特発性てんかん:原因不明で発作が起こり、犬や猫によく見られます。
てんかん発作の定義と一般的な症状
特発性てんかんの発作は、脳の一部もしくは全体が異常に興奮することで起こります。症状は多岐にわたり、全身がけいれんする全般性発作や、一部の筋肉がけいれんする焦点性発作などがあります。
また、意識を失うこともあり、発作が数秒から数分で収まることがほとんどですが、長時間続いたり繰り返し発作が起こったりする場合は、非常に危険です。
犬と猫での発症頻度や年齢層の違い
犬や猫でのてんかん発症率には差があり、症状や発症年齢にも違いがあります。
<犬の場合>
犬では約1〜2%に特発性てんかんが見られるとされています。特にオス犬での発症率が高く、遺伝的な要因が関与しているため、犬種によって発症率が異なります。また、初回の発作が起こるのは6ヶ月から5歳の間に見られることが多く、若齢期に発症することが特徴です。
<猫の場合>
猫では、特発性てんかんの発症率は犬に比べて低く、約0.5%とされています。猫における発症も若年層が多く、6ヶ月から3歳の間に初めて発作が見られることが多いです。猫はてんかんよりも他の病気で発作を起こすことが多いため、発作が確認された場合は他の疾患の可能性も考えながら診断を進めることが重要です。
てんかんと他の発作性疾患との違い
発作を引き起こす病気は、てんかん以外にも存在するため、正確に鑑別することが大切です。
例えば、以下の病気も発作の原因となることがあります。
・低血糖
・肝性脳症
・腎不全
・中毒
・水頭症
・脳腫瘍 など
飼い主様が発作の症状だけで、てんかんなのかそれ以外の病気なのかを見分けるのは非常に難しいため、1度でもけいれん発作が見られた場合は、早めに動物病院を受診することを推奨します。
てんかん発作時の対処法と応急処置
愛犬や愛猫の発作を目の当たりにしたときは、冷静に対応することが大切です。慌てて誤った行動を取ると、犬や猫だけでなく飼い主自身も危険な目に遭う可能性があるため、以下の対処法を覚えておきましょう。
【1. 冷静になること】
まず、飼い主様が冷静になることが重要です。犬や猫は発作中、意識を失っていることが多く、どれだけ声をかけても反応しません。
【2. 周りの安全を確保する】
発作中は犬や猫が周囲の物にぶつかってしまうことがあります。発作が始まったら、近くにある家具や鋭利なものをどけて、けがをしないように安全を確保しましょう。
【3. 直接触らない、薬があれば投与】
発作中は犬や猫に触れると、意図せず噛まれる危険があります。特に口周りは触らないようにしましょう。発作が終わるまで基本的には手を出さず、見守ることが最善です。また、獣医師から発作時の頓服薬を処方されている場合は、投与しましょう。
【4. 記録を取る】
発作の時間や様子を記録することが、診断時に役立ちます。可能であれば発作の様子を撮影し、長さや頻度をメモしておきましょう。
【5. 発作が長引く場合は動物病院を受診】
発作が10分以上続いたり、短時間で何度も繰り返したりする場合はすぐに動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。夜間の場合は、事前に緊急病院を調べておくと安心です。
診断方法
てんかんの診断は問診、血液検査、神経学的検査、画像診断を組み合わせて行います。
<問診>
飼い主様に発作の回数や様子を伺い、てんかんの可能性が高いかどうかを調べます。
<血液検査>
発作の原因が他の病気によるものではないかを確認します。
<神経学的検査>
脳や脊髄など、神経系に関わる別の病気が原因でないかを調べます。この検査は、診察室で動物の体を触診しながら行うもので、無麻酔で実施可能です。
<画像診断(CT検査、MRI検査)>
脳に明らかな病変がないかを確認します。特発性てんかんの場合は異常が見られませんが、症候性てんかんでは脳腫瘍や脳炎などが確認できることがあります。また、この検査は全身麻酔下で行います。
治療方法
治療は抗てんかん薬の投与を行います。抗てんかん薬にはいくつか種類があるため、その子その子の状態に合う適切な薬の種類や量を調整します。また、一度治療が始まると、長期間にわたって発作を管理する必要があるため、飼い主様の協力が非常に重要です。
まとめ
てんかん発作は、飼い主様にとっても犬や猫にとっても非常にストレスのかかる病気です。しかし、適切な治療と管理によって、生活の質を維持することは可能です。そのため、発作が見られた場合は、すぐに動物病院を受診し、獣医師と相談しながら治療を進めていきましょう。また、事前に緊急時の対応を家族で話し合い、冷静に対処できる準備をしておくことも大切です。
広尾・恵比寿・西麻布・南麻布中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」では定期健診に力を入れており、病気の予防と長期健康維持のお手伝いをしております。
「広尾・恵比寿・西麻布・南麻布」を中心に診療を行う
広尾テラス動物病院
当院のWEB相談・お問い合わせフォームはこちらから