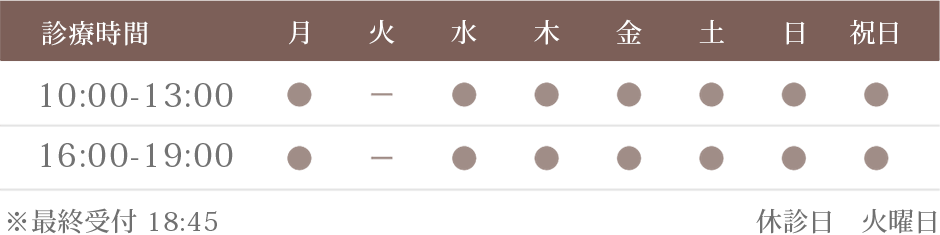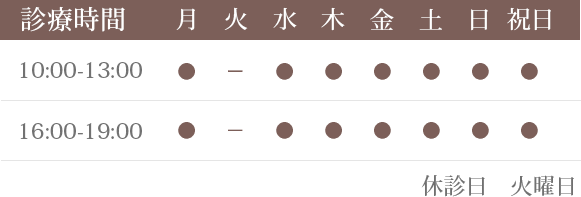BLOG
トイレが頻繁に…|愛犬や愛猫の『多飲多尿』は糖尿病のサイン?!

広尾・恵比寿・西麻布・南麻布を中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」です。
愛犬や愛猫がいつもより頻繁にトイレに行く、または水を大量に飲むといった変化に気づいたことはありませんか?そんな時、考えられる原因のひとつに「糖尿病」があります。多尿多飲は、糖尿病の初期症状として見られることが多いです。そのため、このような症状が見られたら注意が必要です。
今回は犬や猫の糖尿病について、犬や猫それぞれに見られる症状や治療方法、予防法などをご紹介します。
■目次
1.犬や猫の糖尿病について
2.犬の糖尿病
3.猫の糖尿病
4.糖尿病の診断
5.糖尿病の治療方法
6.糖尿病予防と管理:飼い主様ができること
7.まとめ
犬や猫の糖尿病について
犬や猫の糖尿病は、以下のようにそれぞれタイプが異なります。
Ⅰ型糖尿病:遺伝的要因や膵臓の疾患によりインスリンの分泌が不足する
Ⅱ型糖尿病:インスリン自体は正常に分泌されるものの、肥満やストレスなどの環境要因によってインスリンの効果が低下する
犬ではⅠ型糖尿病が多く見られ、猫ではⅡ型糖尿病が多く見られます。
犬の糖尿病
【症状】
犬の糖尿病の主な症状は、以下が挙げられます。
<多飲多尿>
糖尿病の初期症状として、水をたくさん飲む「多飲」と尿の回数や量が増える「多尿」が見られます。このような変化に気づいた場合は、早めに動物病院で診察を受けることが大切です。
<食欲増加と体重減少>
食欲が増える一方で、体重が減少することがあります。これは、食べ物から得た栄養をうまく利用できないために起こる現象です。
<白内障>
糖尿病が進行すると、目が白く濁る「白内障」を発症することがあります。
その結果、視力の低下を招いてしまうことがあります。
<活力の低下>
普段よりも元気がなく、疲れやすくなることがあります。
【原因】
肥満や遺伝要因、ストレスが原因で起こることがあります。また、自己の免疫が膵臓内でインスリンを作る細胞を破壊してしまう「自己免疫性」が原因となることがあります。ほかにも膵臓の疾患や副腎皮質機能亢進症、炎症性の病気なども糖尿病の要因となります。
猫の糖尿病
【症状】
<多飲多尿>
犬と同様に糖尿病の初期症状として、水をたくさん飲む「多飲」と尿の回数や量が増える「多尿」が見られます。
<食欲増加と体重減少>
犬と同様に食欲が増える一方で、体重が減少することがあります。
<活力の低下>
普段よりも寝る時間が増えたり、活動量が減ったりすることがあります。
<消化器症状>
嘔吐や下痢が見られることがあります。
<神経症状>
歩き方に変化が見られることがあり、主にかかとを地面につけて歩く、足に力が入らないといった症状が現れることがあります。
【原因】
肥満や遺伝要因、膵臓の病気、ストレスなどが原因であるといわれています。
糖尿病の診断
<血糖値測定>
空腹時に血糖値を測定し、その値が高ければ糖尿病が疑われます。
<尿検査>
尿中の糖やケトン体の有無を確認します。尿に糖が含まれている場合は、血糖値が高いことを示しています。
<フルクトサミン測定>
過去1~2週間の平均血糖値を反映するフルクトサミンを測定します。この数値によって、長期間の血糖管理状態を確認することができます。
糖尿病の治療方法
犬の場合、治療は基本的にインスリン注射による投与を行います。これはインスリンの不足を補うため、飼い主様が1日に1〜2回必ず注射を行う必要があります。また、食事も糖尿病専用のものに変更します。専用食は、血糖値が急に上がりにくいように設計されています。おやつは基本的には与えないようにしましょう。
猫の場合、インスリン注射が必要となることもありますが、食事管理や体重の減量によって治療が不要になる場合もあります。最近では猫の糖尿病用の経口薬も登場しており、治療の選択肢が広がっています。
糖尿病予防と管理:飼い主様ができること
糖尿病は一度発症すると生涯にわたり管理が必要な病気です。そのため、飼い主様は以下の予防を行うことが重要です。
<食事管理>
バランスの取れた食事を与えることが大切です。肥満が糖尿病の大きなリスク要因となるため、適切な体重管理を行うことが必要です。また、前述したように糖尿病専用のフードに切り替えることで、血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。
<運動管理>
犬の場合、短時間の散歩など適度な運動を行うようにしましょう。猫の場合、室内飼いで運動不足になりがちであるため、おもちゃを使った遊びやキャットタワーなどを利用して、日常的に体を動かせる環境を作ってあげましょう。ただし、過度な運動はかえって血糖値の乱れにつながることもあるため、無理のない範囲で行いましょう。
<定期的な健康チェックなど>
糖尿病は早期発見がカギとなります。そのため、定期的に健康チェックを行い、異常がないか確認することが大切です。また、ご家庭でも体重管理をしっかりと行い、普段の行動に異常が見られた場合はすぐに獣医師に相談することが大切です。
まとめ
愛犬や愛猫が糖尿病になると、飼い主様のサポートが不可欠です。糖尿病を引き起こすと、インスリン注射や食事管理、運動など、日常的に行わなければならないことは多いですが、これらをしっかりと管理することで、犬や猫の生活の質を保つことができます。
普段から糖尿病の早期発見と予防を心がけ、もし症状が見られた場合は早めに動物病院を受診することが大切です。
広尾・恵比寿・西麻布・南麻布中心に診療を行う「広尾テラス動物病院」では定期健診に力を入れており、病気の予防と長期健康維持のお手伝いをしております。
「広尾・恵比寿・西麻布・南麻布」を中心に診療を行う
広尾テラス動物病院
当院のWEB相談・お問い合わせフォームはこちらから